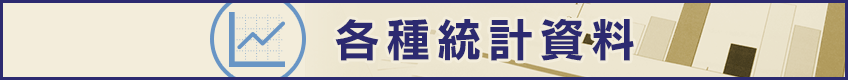全国銀行概況
1.当中間期決算の背景
(1)当中間期中の経理基準の変更等
- 日本公認会計士協会「監査・保証実務委員会報告第42号『租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労金等に関する監査上の取扱い』」(平成19年4月13日付)により、役員退職慰労金に係る会計処理の取扱いが明確化され、平成19年度から適用された(平成18年度末からの早期適用も可)。これを適用した銀行では、「役員退職慰労引当金」が計上されている。
- 証券取引法等の一部を改正する法律(=金融商品取引法)等の施行(平成19年9月30日)に伴い、銀行法施行規則別紙様式が改正され、「金融先物取引責任準備金」および「証券取引責任準備金」を「金融商品取引責任準備金」とする変更が行われた(「特別法上の引当金」の内訳項目であり、中間期決算では掲載していない)。
(2)当期中の金融情勢
平成19年度中間期の金融情勢をみると、短期金利については、19年2月の日本銀行の金融政策決定会合で無担保コールレート(オーバーナイト物)を0.5%前後で推移するよう促すとしたことから、概ね0.5%前後で推移した。
一方、長期金利については、米国の長期金利の上昇や堅調なわが国の経済指標などを受け、6月中旬にかけて1.9%台まで上昇したが、夏以降は、サブプライム住宅ローン問題の影響を受けた欧米の長期金利低下などから低下し、1.5%台から1.7%台の範囲で推移した。
株価は、当初、経済指標や企業の業績発表などを受けて堅調に推移したものの、7月下旬から米国発の世界的な株価下落などを受け、日経平均株価は8月には一時1万5,000円台まで下落した。その後は米国株価や為替相場などを眺めて振れる展開となり、当中間期末の日経平均株価は、16,785円69銭と前年度末(17,287円65銭)比で501円96銭安となった(前中間期末16,127円58銭)。
また、当中間期末の外国為替相場(スポットレート)は、1米ドル=115円27銭となり、前年度末(118円05銭)比で2円78銭の円高となった(前中間期末118円05銭)。
図1 国内主要金利等の推移
![]()
図2 海外主要金利等の推移
![]()
(3)銀行の経営統合等の動き
平成19年5月7日、山形しあわせ銀行と殖産銀行が合併して「きらやか銀行」となった。
担当:小暮
2.概況
(以下は、銀行単体をベースにとりまとめたものである。)
全国銀行124行の平成19年度中間期決算をみると、資金運用益(算式は後掲(注)参照)は、内外の短期金利上昇等を受けて資金運用収益、資金調達費用ともに増加したものの、収益が費用を上回って増加したため、4兆3,006億円(前中間期比1,019億円、2.4%増)と増益となった。
経常利益は、個別貸倒引当金純繰入額や貸出金償却が増加したことに加え、営業経費が増加したこと等から、1兆7,636億円(同4,707億円、21.1%減)と減益となった。
中間純利益は、法人税等調整額(税金費用)は減少したが、前中間期に計上された貸倒引当金戻し益の効果が剥落したこと等から特別利益が減少し、1兆2,186億円(同8,790億円、41.9%減)と大幅な減益となった。
業容面では、預金は期中0.4%減、貸出金は同0.6%増であった。
損益状況
- 資金運用益
- 資金運用益は、4兆3,006億円(前中間期比1,019億円、2.4%増)と、前中間期の減益から増益に転じた。資金運用収益は7兆2,596億円(同1兆1,057億円、18.0%増)、資金調達費用は2兆9,589億円(同1兆38億円、51.3%増)と、いずれも増加したものの、貸出金利回りの上昇を主因として、収益の伸びが上回ったことから増益となった。
内訳をみると、国内業務部門では、利回りの上昇により、貸出金利息、有価証券利息配当金が増加したこと等から資金運用収益が増加し、預金利息が増加したこと等から資金調達費用も増加した。国際業務部門では、残高の増加および利回りの上昇により、貸出金利息、有価証券利息配当金が増加したこと等から資金運用収益が増加し、預金利息が増加したこと等から資金調達費用も増加した。いずれも、収益の伸びが費用の伸びを上回ったことから、国内業務部門、国際業務部門とも資金運用益は増益となった。 - 役務取引等収益・費用
- 役務取引等収益・費用は、個人向けの投資信託の販売手数料等の増加により、法人向け取引における手数料は減少したものの、その収益超過額は1兆500億円(前中間期比123億円、1.2%増)と若干の増加となった。
- 特定取引収益・費用
- トレーディング業務に係る特定取引収益・費用は、国内業務部門、国際業務部門ともに増加し、全体の収益超過額は3,441億円(前中間期比1,491億円、76.5%増)と大幅な増加となった。
- その他業務収益・費用
- 国債等債券関係損益は、国債等の売買損益の改善から、前年の損失超過から収益超過に転じたが、外国為替売買損益は、通貨スワップ取引に係るカバー取引の影響等から収益超過額が減少したことから、その他業務収益・費用全体の収益超過額は、376億円(前中間期比691億円、64.8%減)となった。
- その他経常収益・費用
- 株式等関係損益の収益超過額は減少した。引当金等は、一般貸倒引当金が、前中間期の取崩しから純繰入に転じ、個別貸倒引当金純繰入額、貸出金償却も増加した。その結果、その他経常収益・費用全体の損失超過額は、7,845億円と前中間期(2,551億円の損失超過)に比べて増加した。
- 信託報酬
- 信託報酬は、1,918億円(前中間期比31億円、1.6%増)となった。
- 営業経費
- 営業経費は、物件費、人件費ともに増加し、全体では3兆3,760億円(前中間期比1,385億円、4.3%増)となった。
- 経常利益・中間純利益
- 以上の結果、経常収益は10兆3,299億円(前中間期比1兆2,360億円、13.6%増)、経常費用は8兆5,663億円(同1兆7,067億円、24.9%増)となり、経常利益は1兆7,636億円(同4,707億円、21.1%減)と減益となった(増益56行、黒字転換4行、減益57行、損失7行)。
中間純利益は、法人税等調整額(税金費用)は減少したが、前中間期に計上された貸倒引当金の戻し益の効果が剥落したこと等から特別利益が減少し、1兆2,186億円(前中間期比8,790億円、41.9%減)と大幅な減益となった(増益45行、黒字転換3行、減益66行、純損失10行)。
参考までにみると、業務純益は、2兆5,584億円(前中間期比5億円、0.0%増)と横這いであった。一般貸倒引当金純繰入額を除いた実質業務純益も若干の増益である。
なお、全国銀行の業態別の損益状況は表のとおりである。 - 利回り・利鞘(国内業務部門)
- 資金運用利回りをみると、貸出金利回りが前中間期比0.25%ポイント上昇して1.97%、一方、有価証券利回りは同0.20%ポイント上昇して1.25%、コールローン等利回りが同0.32%ポイント上昇して0.88%となった。この結果、資金運用利回り全体では、同0.23%ポイント上昇して1.67%となった。
資金調達費用をみると、預金債券等利回りが同0.19%ポイント上昇して0.28%、コールマネー等利回りは同0.43%ポイント上昇して0.81%、経費率は同0.05%ポイント上昇して1.11%となった。この結果、資金調達原価全体では、同0.25%ポイント上昇して1.35%となった。
以上の結果、預貸金利鞘は、同0.02%ポイント拡大して0.59%、総資金利鞘は、同0.02%ポイント縮小して0.32%となった。これは、日銀の当預残高の縮減に伴い、貸出金に比べて利回りの低いコールローンの残高が増加したことにより、資金運用利回りの上昇が抑えられたこと等によるとみられる。
資金調達
預金は、期中、国内業務部門では、個人預金が定期性預金を中心に増加したが、法人預金、公金預金の減少から、全体では減少(0.8%減)となった。国際業務部門では増加(4.0%増)した。この結果、預金全体では、末残で555兆1,601億円(前期末比2兆3,983億円、0.4%減)と減少した。
譲渡性預金は、末残で31兆6,724億円(同1兆622億円、3.5%増)となった。
債券は、末残で6兆4,217億円(同5,041億円、7.3%減)となった。
資金運用
貸出金は、期中、国内業務部門では、企業向け貸出が振るわなかったことを受けて減少(0.5%減)したが、国際業務部門では増加(14.2%増)した。この結果、貸出金全体では、438兆2,743億円(前期末比2兆4,127億円、0.6%増)となった。
有価証券は、期中、国債、株式等が減少し、外国証券等は増加したが、全体では195兆4,466億円(同4兆1,718億円、2.1%減)となった。
リスク管理債権(銀行勘定の単体ベース)の残高をみると、破綻先債権額は5,607億円(前期末比75億円、1.4%増)、延滞債権額は7兆4,628億円(同1,889億円、2.6%増)、3カ月以上延滞債権額は1,255億円(同27億円、2.2%増)、貸出条件緩和債権額は3兆3,775億円(同2,990億円、8.1%減)となった。この結果、リスク管理債権の全体は、11兆5,267億円(同998億円、0.9%減)となり、貸出金総額に占める割合は、前期末に比べて0.04%ポイント低下して、2.63%となった。
また、金融再生法第7条に基づき開示が義務づけられている資産査定の各区分の内容は、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が2兆435億円(前期末比3億円、0.0%増)、危険債権が6兆1,964億円(同1,923億円、3.2%増)、要管理債権が3兆5,036億円(同2,960億円、7.8%減)となった。なお、正常債権は462兆1,432億円(同2兆8,266億円、0.6%増)となった。
資本金は、9兆3,080億円(同291億円、0.3%増)となり、純資産の部合計では、その他有価証券評価差額金の減少等から38兆5,871億円(同1兆4,477億円、3.6%減)となった。
なお、繰延税金資産(純額)は、1兆7,700億円(前期末比4,960億円、38.9%増)となった。
担当:世良
注
- 資金運用益=資金運用収益-資金調達費用
- 業務純益=資金運用益+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支+信託報酬-一般貸倒引当金繰入額-債券費-経費-金銭の信託運用見合費用
- 国内業務=国内店の円建取引
- 国際業務=国内店の外貨建取引+海外店の取引(円建対非居住者取引とオフショア勘定は国際業務に含む)
図3 全国銀行の経常利益・資金運用益の推移
![]()
| 全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行Ⅱ | 信託銀行 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資金運用益 | 43,006 (1,019) | 17,807 (699) | 16,649 (246) | 5,299 (△35) | 2,657 (△2) |
| 役務取引等収支 | 10,500 (123) | 5,650 (△107) | 2,678 (112) | 493 (21) | 1,544 (88) |
| 特定取引収支 | 3,441 (1,491) | 3,171 (1,588) | 78 (3) | - (-) | 104 (△64) |
| その他業務収支 | 376 (△691) | 502 (△799) | 21 (264) | △75 (29) | △175 (13) |
| その他経常収支 | △7,845 (△5,295) | △4,535 (△4,341) | △2,245 (△680) | △562 (562) | △670 (△807) |
| 信託報酬 | 1,918 (31) | 62 (11) | 4 0 | - (-) | 1,852 (20) |
| 営業経費 | 33,760 (1,385) | 14,403 (937) | 12,022 (307) | 3,870 (83) | 2,806 (37) |
| 経常利益 | 17,636 (△4,707) | 8,255 (△3,888) | 5,164 (△361) | 1,286 (495) | 2,506 (△790) |
| 中間純利益 | 12,186 (△8,790) | 6,373 (△7,137) | 2,736 (△742) | 782 (421) | 1,914 (△766) |
| (参考)業務純益 | 25,584 (5) | 13,288 (839) | 7,105 (△434) | 1,887 (△19) | 2,941 (△308) |
- 注.
- 上段は平成19年度中間期計数、下段( )内は対前中間期比増減額。