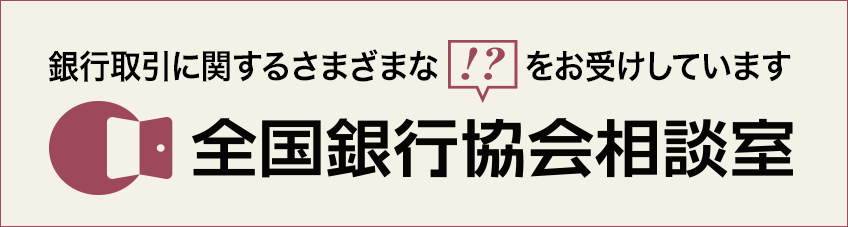苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する運営要領
(目的)
第1条 この要領は、全国銀行協会(以下「本協会」という。)が定める「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」(以下「業務規程」という。)にもとづき、紛争解決等業務を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 なお、この要領で使用する用語は、特段の定めがない限り、業務規程で使用する用語と同じ意味において用いる。
(苦情の申出またはあっせんの申立を受け付けない者)
第2条 業務規程第8条第3項および第4項に定める反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに掲げる場合をいう。
一 次のいずれかに該当したことが判明した場合
〔1〕暴力団
〔2〕暴力団員
〔3〕暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
〔4〕暴力団準構成員
〔5〕暴力団関係企業
〔6〕総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
〔7〕その他前〔1〕から〔6〕に準ずる者
二 自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
〔1〕暴力的な要求行為
〔2〕法的な責任を超えた不当な要求行為
〔3〕加入銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
〔4〕風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて加入銀行の信用を毀損し、または加入銀行の業務を妨害する行為
〔5〕その他前〔1〕から〔4〕に準ずる行為
(個人情報の取扱いに関する紛争の解決)
第3条 本協会は、全国銀行個人情報保護協議会の正会員に係る個人情報の取扱いに関する苦情事案について、同協議会からの依頼にもとづき、あっせん委員会に紛争解決手続を行わせることができる。
2 本協会は、全国銀行個人情報保護協議会との間で、あっせん委員会の利用に関する手続を別に定める。
(苦情対応報告の様式)
第4条 業務規程第9条第3項、第10条第2項および第10条第4項の報告を書面等で行う場合の報告様式等は、別に定める。
(あっせん委員の選任)
第5条 業務規程第15条第1項に定めるあっせん委員の資格要件は、銀行法等の定めによる。
2 業務規程第15条第1項ただし書きに定めるあっせん委員を委嘱することができない者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
四 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
五 弁護士法または外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
六 公認会計士法、税理士法または司法書士法の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分または司法書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
(小委員会の数)
第6条 業務規程第20条第3項に定める小委員会の数は、3以上とする。
(拡大小委員会の審議が必要であると判断する事由)
第7条 業務規程第20条第7項に定める「拡大小委員会の審議が必要であると判断した場合等、別に定める事由が生じた場合」とは、次の各号に該当する場合をいう。
一 請求金額が著しく多額である事案
二 今後同様の内容の事案が複数申し立てられることが予想される事案
三 小委員会の委員間に意見の相違がある事案
四 その他拡大小委員会での審議が相当であると認められる事案
(拡大小委員会の構成等)
第8条 業務規程第21条に定める拡大小委員会の構成員は7名以上10名以下とし、以下のとおりとする。
一 あっせん委員長
二 諮問を行った場合は、当該小委員会のあっせん委員
三 あっせん委員長が指名したあっせん委員(弁護士であるあっせん委員1名、消費者問題専門家であるあっせん委員1名、本協会の役職員であるあっせん委員1名の3名を含む。)
2 拡大小委員会における適格性の審査は書面等により行うことができる。
(小委員会から拡大小委員会への諮問および拡大小委員会から小委員会への再審議依頼)
第9条 業務規程第20条第7項による小委員会から拡大小委員会への諮問および業務規程第21条第6項による拡大小委員会から小委員会への再審議の依頼は、所定の方法により書面等で行う。
(あっせん委員の特別の利害関係)
第10条 業務規程第22条第1項から第3項に定める特別の利害関係とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。
一 当事者またはその配偶者もしくは配偶者であった者
二 当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族もしくは同居の親族である者またはこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人である者
四 紛争解決手続が行われる紛争事案について、当事者の代理人もしくは補佐人である者またはこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者または得ないこととなった日から3年を経過しない者
六 当事者である加入銀行の役職員である者、またはその職にあった者
七 その他前各号に準ずる緊密な関係があるとの理由が明示された者
(書面等を電磁的方法により提出することができる事由)
第10条の2 業務規程第3章の「あっせん委員会事務局が認めたとき」とは、次の各号に該当する場合をいう。
一 情報通信技術に係る安全管理状況等に照らし支障がない場合
二 あっせんの当事者が当該書面等を電磁的方法により提出することで円滑に手続が実施できる場合
(あっせんの申立書および顧客が同意したことを証する書面等の様式)
第11条 業務規程第24条第4項に定めるあっせんの申立書の様式および同条第7項に定める顧客が同意したことを証する書面等の様式は、別に定める。
(苦情処理手続を経ていない事案に関するあっせんの申立て)
第12条 あっせん委員会事務局は、顧客または加入銀行から全国銀行協会相談室における苦情処理手続を経ずにあっせんの申立書の提出を受けた場合には、全国銀行協会相談室にその旨を連携する。当該連携を受けた全国銀行協会相談室は、顧客または加入銀行に対して当該苦情の申し出内容を十分聞き取るとともに、事実関係確認のため、相手方である加入銀行または顧客に連絡する。
2 前項の結果、加入銀行が苦情処理手続による対応を希望した場合には、あっせん委員会事務局は当該あっせん申立てがなかったものとして取扱うことができる。
(あっせんの申立てに係る説明等)
第13条 あっせん委員会事務局は、顧客からあっせんの申立てを受けるに当たり、顧客から次の各号に定める内容について同意を求める。
一 相手方である加入銀行が、あっせん委員会に対し、その所有する顧客に関する資料・証拠書類等の情報を提出し、あっせん委員会が紛争解決手続のためにこれらを利用すること。
二 あっせん委員会が紛争解決手続において必要な場合に、その指定した参考人等に対し、相手方である加入銀行またはあっせん委員会が所有する顧客に関する資料・証拠書類等の情報を提供し、参考人等があっせん委員会からの照会への回答等のために、これらを利用すること。
三 あっせん委員会は、顧客または加入銀行があっせん委員会に対して提出した資料・証拠書類等を、それぞれ相手方に交付し、当事者双方が答弁書、主張書面その他あっせん委員会に提出する書面等を作成するためにこれらを利用すること(ただし、あっせん委員会が相当と認めた場合には、あっせん委員会限りの扱いとすることができる。)。
四 本協会が、関係者のプライバシーに配慮したうえで、あっせん事案の概要等を加入銀行へ通知すること、また公表すること。
2 あっせん委員会事務局は、加入銀行からあっせんの申立てがあった場合に、当該紛争の相手方である顧客に対して意思確認を行う際、顧客から前項各号に定める内容についても同意を求める。
3 あっせん委員会事務局は、顧客または加入銀行からあっせんの申立書1通の提出を受ける際、資料・証拠書類があるときは、その原本または写しの提出も併せて求める。
個人顧客からの申立ての場合には、運転免許証やパスポート等「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める本人確認書類(提出時に、有効なものまたは発行日から6か月以内のもの)の原本またはその写しを、法人顧客からの申立ての場合には、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(発行日から6か月以内のもの)の提出を求める。
4 前項後段の規定は、あっせんの申立てを行う代理人についても同様とし、さらに顧客本人との関係を示す資料(戸籍謄本等)を求める。
(答弁書の様式)
第14条 業務規程第25条第3項に定める加入銀行が作成する答弁書の様式は、別に定める。
(主張書面の様式)
第15条 業務規程第26条第5項に定める主張書面の様式は、別に定める。
(紛争解決手続を行わない場合等)
第16条 業務規程第27条第1項第二号の「訴訟が終了」について、その終了原因によっては同号に該当しないとあっせん委員会が判断する場合がある。
2 業務規程第27条第1項第四号の「他の指定紛争解決機関や紛争の解決を実施する外部機関によるあっせん、仲裁等」について、紛争の当事者以外の第三者があっせん案を提示することなく、仲介を主としたあっせんのみを行うような場合には、同号に定める「手続の終了」には該当しないとあっせん委員会が判断する場合がある。
3 業務規程第27条第1項第六号の「加入銀行の経営方針や融資態度、あるいは銀行員等個人に係わる事項等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
一 銀行業務等に係わらない事案(銀行株等への投資等)
二 融資申込みや条件変更等が審査の結果断られた事案
三 口座開設・海外送金の申込みが断られた等の加入銀行の取引方針に関する事案
四 特定行員の素行や接客態度に関する事案
五 単に謝罪のみを要求するような事案
六 その他前各号に準ずる事案
(加入銀行が支払う事案手数料)
第17条 業務規程第28条第1項に定める加入銀行が支払う事案手数料は、10万円(消費税等は非課税)とする。ただし、事案の内容や背景、当事者の事情、その他特別の事情がある場合であって、紛争解決手続に特別の対応を要する場合には、予め当事者である加入銀行の同意を得たうえで、この手数料を200万円を超えない範囲内で増額することができる。
2 あっせん委員会があっせんの申立てを受理した後、あっせん委員会事務局は所定の方法により加入銀行に事案手数料を請求する。
(あっせん委員会への出席)
第18条 あっせん委員会の事情聴取は、当事者に対し、予め出席すべき日時・場所等を通知したうえで行う。なお、事情聴取をウェブ会議などの電磁的方法で実施する場合(あっせん委員会事務局が用意する端末等を利用する場合を除く)には、あっせん委員会事務局は、期日の3営業日前までに、当事者が別に定める事項に同意していることを所定の書面等(様式は別に定める)で確認しなければならない。
2 あっせん委員会事務局は、前項の通知を遅くとも期日の5営業日前までに行わなければならない。
3 当事者は、事情聴取に際し代理人または補佐人とともに出席することが適切かつ必要とする旨の申出をする場合には、所定の書面等(様式は別に定める)および当事者との関係を示す資料を期日の3営業日前までに提出し、あっせん委員会の判断を仰がなければならない。
4 前項により、あっせん委員会が代理人または補佐人の出席を認めた場合にはその旨を、認めなかった場合にはその理由とともに、あっせん委員会事務局から当事者に通知する。
5 あっせん委員会に出席する当事者等は、委員または他の出席者を困惑させる等の不適切な言動をしてはならない。
6 当事者またはその代理人は、指定された事情聴取に出席できない場合には、あっせん委員会事務局に対して予め電話連絡を行ったうえで、当該期日の3営業日前までにその旨と理由を記載または記録した書面等(様式任意)をあっせん委員会に提出しなければならない。
7 あっせん委員会は、前項の通知を受け、改めて事情聴取のための期日を定める場合には、当事者に通知する。
(あっせんの申立取下書等および顧客が同意した書面等の様式)
第19条 業務規程第32条第1項および第4項に定めるあっせん申立取下書の様式、同条第1項に定めるあっせん申立同意撤回書の様式、ならびに同条第4項に定める顧客があっせんの申立てを取り下げることに同意した書面等の様式は、別に定める。
(特別調停案の取扱い)
第20条 業務規程第35条第1項に定めるあっせん委員会が特別調停案を提示することについて「相当であると認めるとき」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。
一 加入銀行が、あっせん委員会が提示したあっせん案(あっせん委員会が提示することを予定しているあっせん案を含む。)を受諾しないことについて、正当な理由がないと判断する場合(ただし、この場合において、顧客が不受諾の意向を示しているときを除く。)
二 顧客が、紛争解決手続による解決を希望している場合において、加入銀行から当該事案について訴訟を提起されることを容認しているとき
2 業務規程第35条第2項に定める「その他特別調停案の取扱い」とは、以下の各号に定めるものをいう。
一 あっせん委員会が提示した特別調停案に対し、当事者双方が受諾した場合には、業務規程第36条により、あっせん委員会は遅滞なく和解契約書の作成等を行う。
二 あっせん委員会が提示した特別調停案に対し、銀行法等の定めにより、受諾しない事由に該当することを証する書面等を提出して加入銀行のみが不受諾とした場合、または当事者双方が不受諾とした場合には、業務規程第37条第2項により紛争解決手続を終了し、その旨を当事者双方に通知する。
(あっせん委員会の運営に関する特則)
第21条 あっせん委員会の運営に当たり、業務規程およびこの要領に定めのない事項は、あっせん委員会の決定による。
(全体会・分科会の構成員等)
第22条 業務規程第42条に定める全体会および分科会の構成員は、次の各号のとおりとする。
一 全体会の構成員は、全てのあっせん委員とする。
二 分科会の構成員は、あっせん委員長が指名した3名以上のあっせん委員とする。
2 あっせん委員長は、全体会または分科会の開催が必要であると判断した場合には、これらを招集することができる。
3 全体会および分科会にはあっせん委員のほか本協会の役職員が出席することができる。
(他の指定紛争解決機関への苦情・紛争事案の取次ぎ等)
第23条 業務規程第43条に定める他の指定紛争解決機関への取次ぎに当たり、顧客からの苦情の申し出または紛争の解決の申立ての内容が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める先に取り次ぐものとする。
一 生命保険業務(ただし、加入銀行の募集行為を原因とするもののうち、別に定める要件に該当するものを除く。)に関するものである場合
生命保険協会
二 損害保険業務(ただし、加入銀行の募集行為を原因とするもののうち、別に定める要件に該当するものを除く。)に関するものである場合
日本損害保険協会または保険オンブズマン
三 信託業務に関するものである場合
信託協会
四 前三号以外の業務で、他の指定紛争解決機関において、苦情処理手続または紛争解決手続を行うことが適切であると判断した場合
当該指定紛争解決機関
2 加入銀行における保険商品の窓口販売業務、信託業務および登録金融機関業務に関する全国銀行協会相談室における苦情処理手続およびあっせん委員会における紛争解決手続について、他の指定紛争解決機関への取次ぎ等に当たって必要な事項は、別に定める。
(苦情処理および紛争解決手続に関する記録の保存期間)
第24条 業務規程第44条第1項に定める全国銀行協会相談室における苦情の受付とその対応状況の記録の保存期間は5年間、業務規程第40条第1項に定める手続実施記録および業務規程第44条第2項に定めるあっせん委員会事務局における紛争解決手続についての経過の要領および結果の記録の保存期間は、10年間とする。
(業務規程の不遵守に係る報告様式)
第25条 業務規程第46条第1項の報告様式は、別に定める。
(苦情・紛争連絡担当部署等の届出様式)
第26条 業務規程第50条の届出様式等は、別に定める。
(特則)
第27条 業務規程およびこの要領の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営要領の改正)
第28条 この要領の改正は、本協会業務委員会の決議による。
附則(平成22年9月8日)
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日)
この改正は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日)
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月18日)
この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月16日)
この改正は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日)
この改正は、令和3年3月1日から施行する。
附則(2022年3月15日)
この改正は、2022年4月1日から施行する。
附則(2022年12月13日)
この要領の改正は、2023年4月1日から施行する。
附則(2025年5月13日)
この要領の改正は、2025年7月28日から施行する。