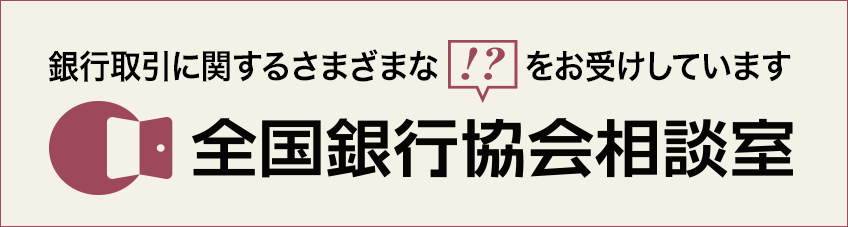あっせん委員会について
1.「あっせん」とは
あっせんとは、お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルを中立・公正な第三者で構成する「あっせん委員会」が、「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」にもとづき、当事者からの資料の提出やそれぞれの主張を聴取したうえで、あっせん案(和解案)を提示し、双方が納得したうえで、解決を図る制度です。なお、「あっせん委員会」があっせん成立の見込みがないと判断した場合等には、紛争解決手続を打切ることがあります。
2.「あっせん委員会」とは
「あっせん委員会」は、弁護士、消費者問題専門家、金融業務等に係る有識者等で構成される中立・公正な委員会です。あっせん委員を選任する際には、すべてのあっせん委員候補者に対し、あっせん委員会運営懇談会外部有識者委員またはあっせん委員が面談し、中立・公正な立場で判断ができるか、また加入銀行との特別な利害関係がないことなど、あっせん委員としての適性を十分に確認したうえで、選任を行っています。
事案ごとにあっせん委員がお客さまと銀行(当事者)との間で特別な利害関係がないことを確認しており、「あっせん委員会」の中立性・公正性を確保しています。
3.「あっせん委員会」のご利用
全国銀行協会相談室が苦情を受け付け、銀行に対応を求め、その結果についてお客さまのご納得が得られない場合、または苦情の申し出から2か月以上経過しても解決していない場合、お客さまからその旨のお申し出があれば、相談員は、お客さまに「あっせん委員会」のあっせんを受けることができること、その利用に当たっては適格性審査があることをご説明し、あっせんの利用申込みに関するお客さまのご意向を確認いたします。
お客さまが「あっせん委員会」へのあっせんの申立てを希望されたときは、全国銀行協会相談室の苦情処理手続は終了することをご説明します。
あっせん委員会では、銀行法および指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針にもとづき、お客さまからのお申立内容を、個人が特定されない形で公表させていただきます。あらかじめご了承ください。
4. 「あっせん委員会」による紛争解決手続の流れ
あっせんの申立ては、全国銀行協会内のあっせん委員会事務局のみで受け付けています。全国銀行協会以外の各地の銀行協会では、あっせんの申立てを受け付けることができませんので、ご留意ください。
紛争解決手続の手数料は、無料です。手続とは別に、あっせん委員会の事情聴取に出席するための交通費、郵送費、コピー代、本人確認書類を用意するための費用などは、お客さま自身のご負担になります。
あっせん委員会の会場は、東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、高松、広島、福岡の8か所に設置されています。それ以外の地域でも、最寄りの銀行協会等で、電話会議やウェブ会議などの通信手段によって事情聴取を行うことができます。
(1)あっせん委員会をご利用いただくには
全国銀行協会相談室(以下「全銀協相談室」)による苦情処理手続を経ても、銀行とのトラブルが解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。全銀協相談室による苦情処理手続に先行して、あっせん委員会による紛争解決手続を行うことはできません。
(2)全銀協相談室からの紛争解決手続の説明
全銀協相談室は、あっせんの申立てを希望するお客さまに対し、紛争解決手続等の説明を行います。銀行に対しては、お客さまがあっせんを希望されている旨を伝えます。
(3)申立書等の作成・送付
お客さまにおかれては、あっせんの申立書を作成のうえ、資料・証拠書類、本人確認書類を添付して、あっせん委員会事務局までご郵送いただきます。申立書はお客さまの個人情報等の取扱に関する同意書を兼ねています。
提出書類の様式は、すべて全銀協ホームページからファイルをダウンロードできます。必要であれば郵送いたしますので、あっせん委員会事務局までご連絡ください。
(4)申立てに関するご照会
あっせん委員会事務局は、あっせんの申立ての趣旨を確認するため、申立書の内容についてお客さまにご照会させていただくことがあります。
(5)銀行への参加要請、答弁書の提出
あっせん委員会事務局は、銀行に申立書等の写しを送付して紛争解決手続に参加することを要請します。銀行は、答弁書を作成し関係資料とともに、あっせん委員会事務局に提出します。
(6)適格性の審査
銀行から答弁書を受領した後、あっせん委員会は申立てに係る適格性の審査を行います。ただし、明らかに「紛争解決手続を行わない」事由に該当するとあっせん委員会が判断した場合には、銀行への参加要請および答弁書提出を求めずに適格性の審査を行い、紛争解決手続を行わないこととして手続を終了することがあります。
適格性の審査の結果、あっせん委員会がお客さまの申立てを受理しないこととしたときは、お客さまにその理由を付して書面でご通知します(紛争解決手続は終了となります)。
(7)あっせん申立ての受理
適格性の審査の結果、あっせん委員会がお客さまの申立てを受理したときは、銀行の答弁書とともにその旨をご通知します。
(8)主張書面や資料等のご提出
あっせん委員会は、お客さまと銀行に対して、相手方の主張に対する反論等を記載した主張書面、追加の資料・証拠書類等の提出を求めます。
あっせん委員会事務局は、お客さまと銀行から提出された主張書面、資料・証拠書類等をそれぞれ相手方に送付します。
(9)事情聴取のためのあっせん委員会への出席
あっせん委員会は、お客さまと銀行の出席を求め、予めお知らせした日程において事情聴取を行います。
出席を求められたお客さまと銀行は、原則として自ら出席しなければなりません。
あっせん委員会は、お客さまと銀行からそれぞれ個別にお話を伺います。原則としてお客さまが銀行と対面してお話をする機会はありません。
(10)打切り
和解が成立する見込みがないとあっせん委員会が判断した場合は、あっせんを打切りとし、その旨を書面でご通知します。
(11)あっせん案の提示
あっせん委員会は、当事者双方の主張をお伺いし、お互いの互譲により歩み寄りが可能な場合には、あっせん案をご提示します。
あっせん案の提示を受けた銀行はこれを尊重し、正当な理由なく拒否してはならないこととされています。
また、あっせん委員会の判断により、特別調停案を提示することがあります(銀行は、訴訟を提起する場合等、銀行法第52条の67第6項に規定する場合を除き、これを受諾する義務があります)。
(12)和解契約書の作成
あっせん案を当事者双方が受諾したとき(あっせん成立)は、あっせん委員会は和解契約書を3通作成し、お客さま、銀行およびあっせん委員会(小)委員長がそれぞれ押印します(和解契約書の締結により紛争解決手続は終了します)。
お客さまからの申立書を受け付けてから和解契約書の締結までの所要期間は、概ね6~8か月程度です(申立ての内容等によって所要期間は異なります)。
(13)紛争解決手続の終了
〔当事者の不受諾〕
お客さまと銀行の一方または双方があっせん案を受諾しなかった場合は、あっせん不成立により紛争解決手続は終了します。
〔取下げ〕
お客さまは、あっせん申立取下書を提出することにより、いつでもあっせんの申立てを取り下げることができ、紛争解決手続は終了します。
5.全国銀行協会の「あっせん委員会」ご利用に当たっての留意事項
(1)プライバシー(秘密)の取扱方法
申立書の記載内容、あっせん委員会での発言内容における当事者および第三者のプライバシー(法人の場合には、事業・財産等)等にかかる秘密情報は、あっせん委員やあっせん委員会事務局の担当者には秘密保持義務が法的に課されていること、資料等も厳重に保管していることから、外部に漏れることはありません。
(2)時効の中断効
「あっせん委員会」へ申立てを行ったものの、あっせん委員会が当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決手続を打ち切って終了した場合、紛争解決手続が終了した旨の通知を受けてから1か月以内に訴訟を提起したときは、あっせん委員会への申立てのときに訴訟の提起があったものとみなされます。
(3)他の指定紛争解決機関への取次
あっせん委員会は受け付けた紛争が他の指定紛争解決機関における手続に付することが適当と判断した場合は、お客さまのご希望を確認のうえ、他の指定紛争解決機関に取り次ぐことがあります。
(4)反社会的勢力への対応
お客さまが反社会的勢力であることが明らかになった場合や、あっせん委員またはあっせん委員会事務局の担当者に対し、恫喝、脅迫または誹謗中傷する言動があった場合、また公序良俗や社会的公正性に反する行為等に関連する事案の場合などにおいては、あっせん委員会は紛争の申立てには応じられません。
6. 全国銀行協会の紛争解決等業務に関する異議受付窓口
全国銀行協会では、全国銀行協会相談室が行う苦情対応やあっせん委員会が実施する紛争解決の業務について、その手続等に関するお客さまからの異議を下記の窓口で受け付けています(相談・照会、苦情、あっせん委員会が実施する紛争解決の業務の窓口ではありません)。
この窓口では、手続等に関するお客さまからの異議(業務規程の規定と異なる手続が行われている等)を受け付けており、個別の苦情・紛争事案の結果に対する不満足の表明等(例えば、和解案の内容が納得いかない、あっせんの打切りとなったことが納得いかない等)の受付はいたしません。