ファイナンシャル・プランナーからのアドバイス
- 「高等教育の修学支援新制度」により給付型奨学金の内容拡充
- 自治体や大学などで実施している給付型奨学金も調べておきたい
- 貸与型奨学金も選択ついては親子で十分な話し合いを
「長男が来年大学受験を控えています。できれば全額、学費は負担してあげたいのですが、住宅ローンも抱え、私立に進むと教育資金が足りるかどうか不安です。返還が不要の奨学金があると聞きましたが、どうすれば利用できるのでしょうか?(女性/43歳)」
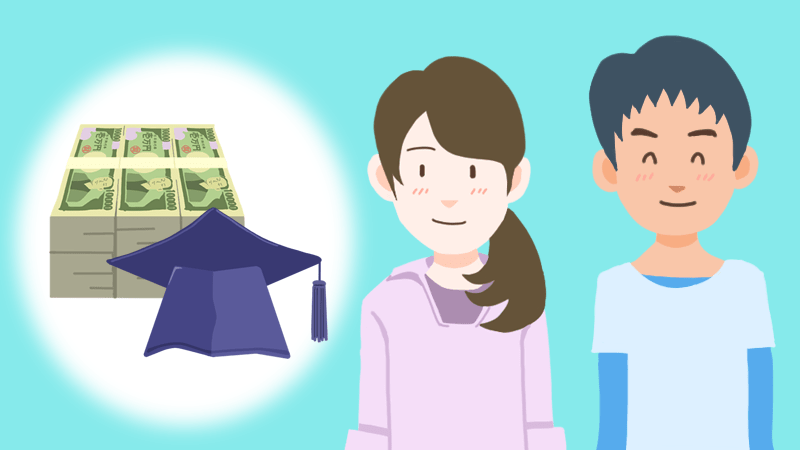

国の奨学金制度を運営している独立行政法人・日本学生支援機構は、2017年度からは従来の貸与型に加え、返還不要の「給付型奨学金」を開始しました。そして、2020年度には「高等教育の修学支援新制度」がスタート。給付型奨学金はより支援要件が緩和され、また支給額も増えました。
奨学金支給の対象となるには、世帯収入と対象者の学力の2つの要件を満たす必要があります。新制度以前は「住民税非課税世帯(※1)」が対象でしたが、新制度ではそれに準ずる世帯も加わりました。学力では、一定の基準を満たすことに加え、それを満たさなくともレポート等で本人の学修意欲が確認できることを要件としています。
支給額は、例えば私立大学の場合、新制度以前であれば、自宅通学が月額で3万円、自宅外通学が4万円でしたが、新制度により自宅通学3万8,300円、自宅外通学7万5,800円となりました(金額は住民税非課税世帯の場合。表1参照)。また、住民税非課税世帯に準ずる世帯では、世帯年収によって上記金額の2/3または1/3の給付額(※2)となります。
加えて、「高等教育の修学支援新制度」では、新たに「授業料等減免」も実施されます。大学等に進学する際の入学金と授業料を減免するというもので、私立大学の場合、卒業までに上限306万円が減免されます(表2参照)。要件は給付型奨学金と同様で、併用も可能です。
ともに利用には申し込みが必要となります。要件や申し込みの日程等を、在籍する高校と早めに相談、確認をしておきましょう。
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
|---|---|---|---|
| 大学・短期大学・専門学校 | 国公立 | 2万9,200円(3万3,300円) | 6万6,700円 |
| 私立 | 3万8,300円(4万2,500円) | 7万5,800円 | |
| 高等専門学校 | 国公立 | 1万7,500円(2万5,800円) | 3万4,200円 |
| 私立 | 2万6,700円(3万5,000円) | 4万3,300円 | |
(※)生活保護世帯で自宅から通学、または児童養護施設等から通学する人は( )内の金額
| 国公立 | 私立 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
| 大学 | 28万2,000円 | 53万5,800円 | 26万円 | 70万円 |
| 短期大学 | 16万9,200円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
| 高等専門学校 | 8万4,600円 | 23万4,600円 | 13万円 | 70万円 |
| 専門学校 | 7万円 | 16万6,800円 | 16万円 | 59万円 |
(※)入学金の免除・減額を受けられるのは入学月から支援対象となった学生。
夜間制、通信教育課程は入学金、授業料の減免額が異なる。 表1・表2ともに文部科学省「授業料等減免額(上限)・給付額奨学金の支給額」より
内容が拡充されたとは言え、「高等教育の修学支援新制度」での給付型奨学金や授業料等減免は、ともに経済的利用で大学等の進学が困難な生徒が対象となります。ご相談者のように、住宅ローンなど家計支出が多く、結果、教育資金が用意できない可能性がある世帯であっても、一定以上の世帯収入があれば原則、その対象となることはできません。
ただし、給付型奨学金は、日本学生支援機構の他にも大学や自治体、その他団体でも実施している場合があります。入学金、授業料の減免について独自に行っている大学もあります。事前に調べてみることをおすすめします。
また、家計状況等によっては、返還義務のある従来の「貸与型奨学金」の利用を検討されるかもしれません。2017年度以降は、日本学生支援機構では、年収に応じて返還月額が変わる「所得連動返還方式」を加えるなど、より利用しやすい制度となっています。それでも、貸与型は返還義務があり、将来お子さん自身の負担になることに変わりはありません。親子でよく話し合い、無理のない内容で利用するよう心掛けてください
(※1)生計を維持する人(2人いる場合は2人とも)の住民税(所得割)が非課税(0円)となる世帯。他に、社会的養護を必要とする人(児童養護施設退所者等)も含む
(※2)両親、本人、中学生の4人家族の場合、目安として世帯年収が約270万円以下を住民税非課税世帯とし、世帯年収が約270万〜約300万円の世帯が2/3、約300万〜約380万円の世帯が1/3の給付に該当。
